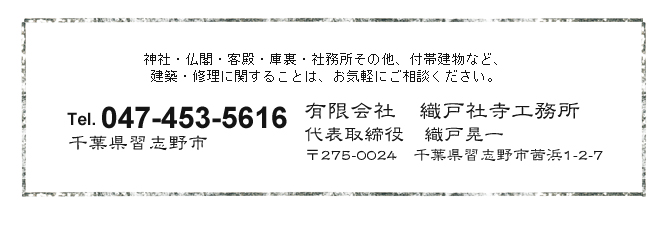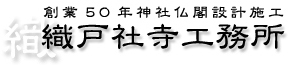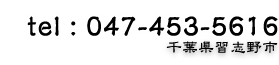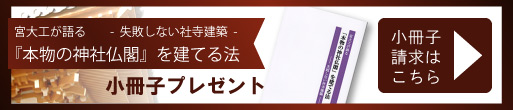建長寺 禅堂・侍者寮 新築工事
  |
建長寺 施工内容禅堂(大徹堂)・侍者寮 新築工事
|
「禅宗様」を忠実に再現する施工でした。斗供の「丸み」や屋根の「反り」にも禅宗様式の独自性をしっかりと表現するため、原寸図検査の時点で細部までこだわり、完成した建物は美しく、かつての禅堂の面影を表現する建物となりました。
ご依頼の経緯
以前よりお付き合いのある(株)中島工務店様より、木工事施工の相談を受けました。工期の問題もあり、禅堂は、八野大工様と共同で施工。侍者寮は当社で施工することになりました。
工夫したこと
今回の工事は禅宗様式の独自性を完璧に再現するため、設計士が詳細な設計図を制作したものでした。大工としては設計士とよく打合せをしながら、詳細な図面にしたがって工事を進めてゆきました。斗供の「丸み」や屋根の「反り」の一つひとつを丁寧に施工し、荘厳な雰囲気を醸し出すように心を込めました。
禅堂新築工事アーカイブ

当社の工場に部材が運び込まれた様子。

仕口(しぐち)。部材を延長する「継手」に対し仕口は、部材が交差する部分に施す細工です。

継手(つぎて)。桁や土台などの横物の部材を延長するための細工です。材木に沿って入っているスリットは、木が見える場所にひび割れが出ないようにするための背割(せわり)です。

隅木(すみぎ)。屋根の四隅に斜めに出っ張ている部分に使われる重要な部材です。

隅木(すみぎ)の下端(したば)になる部分です。

鎹(かすがい)で部材を止めています。この鎹は、鍛冶屋が昔ながらの方法で手打ちで作られました。

和釘(わくぎ)です。これも、鍛冶屋が昔ながらの方法で手打ちで作られました。手前にある普通の釘と比べても、その違いがわかります。

隅木の上に乗っている、反り上がっている部材は、茅負(かやおい)と言います。屋根の反り・曲線を演出し、屋根の重量を支えるという重要な部材です。

斗供(ときょう)や斗組(ますぐみ)と言われる、社寺建築特有の部材です。見栄えが良くなりますが、これでも簡素な方です。このお寺の様式で、簡素な斗供を採用しました。一見不安定のように見えますが、免震に一役買っていると言われています。

屋根の四隅に魔除けの餅を置いたところ。そろそろ上棟式が始まります。

上棟式の祭壇の様子です。

上棟式のときに、職人が使う儀式用の道具です。

屋根が完成しました。隅棟(すみむね)の鬼瓦に、法輪があしらってあります。
その他の社寺建築実績